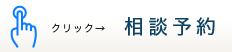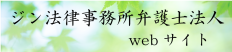裁判例
裁判例紹介
元経営者による水増し請求と不法行為
元経営者が、関連会社などを使って水増し請求をして利益を得た行為の違法性が争われた裁判例です。
会社の代表者が代わり、旧代表者に対して責任追及をしていくような場合に参考になるかと思います。
判決の中で、競艇事業のお金の流れも触れられていますので、興味がある方はチェックしてみると良いでしょう。
京都地方裁判所平成27年6月12日判決です。
事案の概要
原告は、警備会社にボートレースの場外発券場の警備委託料を支払っていました。
原告の取締役であった被告Y1、Y2が委託料水増し請求をし、水増し部分をキックバックさせて、取得していたとして、共同不法行為等に基づく損害賠償請求をした事案です。
裁判所の結論
被告らの共同不法行為責任等を認め、約1億8000万円の損害賠償を命じました。
どういう当事者?
原告は、場外舟券売場施設の賃貸業等をしていた株式会社。
場外舟券売場施設であるボートピア(ボートレースの場外発券場)を所有。
被告らは、原告の取締役であったほか、別会社の代表取締役にもなっていあmsちあ。
一時期は、原告の代表取締役でもありました。
ボート場外発券場の開業と報奨金
本件ボートピアの誘致及び開業の計画には、H、被告Y1、被告Y2も参加していました。
原告においては、被告Y1、被告Y2も、本件ボートピアの開業についての功労者として扱われていました。
本件ボートピア開業には、4年数か月の年月がかかったようです。
原告は、被告らを含めた功労者に対し、本件ボートピアの開業についての報奨金を支払うこととしました。
各功労者が報奨金支払先として準備した各会社との間で実体のない業務協定を締結。
以後、業務委託料名目で、毎月、上記各社に報奨金を支払い続けたのです。
このシステムについては、原告の全ての社員(出資者)及び株主が同意。
ボート場外発券場運営による収益は?
本件ボートピアは、施行者である滋賀県が、社団法人滋賀県モーターボート競走会に運営を委託。
競走会が、施設所有者である原告に、舟券の発売及び払戻設備等の調達・保守委託、警備補助業務、清掃業務等の運営に関する業務の一部を原告に再委託する形式で運営。
滋賀県から競走会に、競走会から原告に対し、それぞれ毎月業務委託料が支払われ、これが原告の収益となっていました。
警備委託契約の締結と終了
原告は、警備会社との間で警備委託契約を締結。
本件警備委託契約に関しては、原告において、警備委託料の金額が異なる2通の契約書が保管されていました。
そのうちの1通の契約書においては、警備委託料が1時間当たり1860円。
もう1通の契約書においては、警備委託料が1時間当たり1350円とされていました。
原告は、警備会社に対し、前者の契約書に基づき、1時間当たり1860円の警備委託料を支払いました。
その後、単価を1500円に減額する合意がされています。
さらに、減額交渉が行われ、1時間当たり1350円の警備委託料とされました。
被告らへの送金
警備会社は、原告から受領した警備委託料につき、その一部を、毎月、警備業務営業支援費用名目で、被告らの関連会社に送金していました(合計1億7980万5740円)。
これらの金員は、実質的に被告Y1、被告Y2が取得していたといえます。
このような支払について、原告の社員総会、株主総会及び取締役会で承認された形跡はありませんでした。
税務調査と修正申告
原告は、大阪国税局の税務調査を受けました。
そのなかで、警備会社に対して支払った本件警備委託料のうち、警備会社が被告らの関連会社に送金した金員については、原告が本件警備委託料の一部をバックしてもらっていたものであり、警備委託との対価性がなく寄付金と認められるので、その経費性を否認するとの指摘を受けました。
原告は、大阪国税局からの上記指摘を踏まえ、大阪国税局から経費性を否認された送金合計額を損害賠償請求権として計上する旨の修正確定申告をしました。
刑事告訴と不起訴
ここから、原告は、まず刑事手続で動きました。
本件システム実施について、被告Y1と被告Y2を特別背任罪で刑事告訴。
しかし、京都地方検察庁検事は、不起訴処分(嫌疑不十分)にしました。
民事訴訟提起と被告の反論
そこで、 原告は、民事手続きとして、本件訴訟を提起したという経緯です。
これに対して、被告らは、損害賠償請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をするなどしています。
この事件の争点としては、
そもそも本件システムに違法性があるか?
すなわち、原告の社員(出資者)ないし株主全員の同意があったか
という点があります。
上乗せの違法性は?
原告は、原告の資産を移動させるシステムであることから、原告として資金移動の実体を把握することができず、当時及び将来の出資者を欺いて私腹を肥やすものであるというほかはなく、取締役の報酬決定方法を定めた会社法361条1項に違反した違法な金員の受領であると主張。
これに対して、被告らは、原告の社員(出資者)ないし株主の全員が本件システムにつき同意しているから、本件システムは違法性がないと主張しました。
しかし、客観的には、このシステムには、同意があるという証拠はありませんでした。
むしろ、一部の出資者は、この送金システムの説明を受けた後、その中止を指示していました。
したがって、本件システムにつき、本件システム開始当時の全株主の同意があったとはいえないと認定しています。
本件システム開始当時、被告Y2は原告の代表取締役、被告Y1は原告の取締役であ、原告に対して、忠実義務(会社法355条)、善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負担していたと認定。
被告Y1及び被告Y2は、本件システム実施につき、会社法423条1項に基づく損害賠償責任を負うものであり、また不法行為責任も負っているとしました。
損害額については?
原告に発生した損害額がいくらなのか、という点も争点となりました。
原告は、競艇事業の収入の仕組みから損害を主張しました。
まず、競艇事業は、モーターボート競走法により舟券売上金の75%以上を払戻金とすることが定められています。
ギャンブルの期待値等でも出てきますが、運営側が一定の経費を差し引くわけです。
すなわち、賭けたお金は、基本的には75%になり、そこから当選するかどうかによって払戻金が決まるという仕組み。そこから、損をする可能性が高いという話がされます。
本件ボートピアで獲得した残り25%の収益の配分については、びわこ競艇の施行者である滋賀県と競走会と原告との間で覚書が作成されていました。
この覚書では、法定交納付金、滋賀県の収益、競走会の収益は、売上に応じて配分が決まっており、残りの開催経費から競走会が負担する経費を差し引いた金員が原告に支払われ、そこから原告は、売上の5.5%で計算される施設賃貸料の取得と、経費支払を行うことになっていました。
すなわち、まず滋賀県が、施行者が支払うべき経費(法定交納付金5.618%、環境整備協力金1%、現金輸送経費)を支払い、その後、施行者収益(1日の売上げ2500万円までは2%、2500万円を超える部分は4%)を取得した上で、残額を委託料として競走会に支払います。
次に、競走会は、滋賀県から受けた委託料の中から、競走会が支払うべき経費(オペレーター人件費、事務所人件費、消耗品費、トータリゼータシステム保守料、中央情報システム利用料、放映委託料、広告宣伝費、施設借上料(売上金の5.5%))を支払い、その後、競走会事務委託料(1日の売上げ2500万円までは0.5%、2500万円を超える部分は1%)を取得した上で、残額を委託料として原告に支払います。ただし、本件ボートピアの施設は原告所有であることから、施設借上料は原告に対して支払われます。
原告は、競走会から受けた委託料の中から、原告が支払うべき経費(アテンダー人件費、警備委託料、清掃委託料、廃棄物収集運搬処分費、送迎バス関係費、発売設備リース料、映像設備リース料、広告宣伝費、光熱水費・消耗品費その他)を支払い、なお残額がある場合は、事務補助費として原告の収入となるのです。
判決にも記載された計算式は次のとおりです。
売上金の25%-(滋賀県が支払う経費+施行者収益)-(競走会が支払う経費+競走会事務委託料)-原告が支払う経費(警備委託料が含まれる。)=原告の収入となる事務補助費
すなわち、原告は、競走会から支払われた開催経費をその原資として、競走会から委託された業務を他社へ再委託するなどして遂行しており、上記原資から上記業務の再委託に係る経費を差し引いた金額が原告の利益となります。
したがって、原告から再委託先への支払額が減少すれば原告の利益は増加するという仕組みです。
警備会社へ支払った警備委託料の中に、警備委託業務の対価とは別に被告Y1及び被告Y2の私益になる金員が上乗せされていた部分があるとすれば、その分原告の得る利益が減少し、原告に損害が生じていたことになります。
原告は、警備会社が自社の利益を削ってキックバック金を捻出したのではなく、被告Y1及び被告Y2と共謀して、キックバック金相当額を上乗せした過大な警備委託料を設定して原告に支払わせていたと主張しました。
そこで、上乗せした送金額が損害になると主張しました。
判決でも、概ねこの主張が認められ、原告が主張する金額に違い額が損害額として認定されています。
原告の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は?
被告らは、原告が主張する被告らの不法行為は、被告Y1及び被告Y2と共に本件システムを構築したことに尽き、それは本件警備委託契約の締結と同時に行われていたこと、原告は、システム構築と同時にその存在を認識していたことから、警備委託契約が締結時から3年の消滅時効が既に完成していると主張しました。
また、仮に、警備委託料の現実の支払があった時点が消滅時効期間の起算点だとされる場合には、3年経過分については消滅時効が完成しているとも主張しました。
これに対し、原告は、法人の代表者が法人に対する共同不法行為者である場合は、自己が行った不法行為を暴露し、共同不法行為者に対して損害賠償請求権を行使することを社会通念上期待し得ないことは明らかだと主張。
単に、法人の代表者が損害及び加害者を知るのみでは足りず、法人の利益を正当に保全する権限のある上記代表者以外の役員または従業員において、損害賠償請求権を行使することが可能な限度にこれを知った時から消滅時効期間が進行すると解するのが相当と主張しました。
具体的には、大阪国税局の担当官よりこれを説明された時期が起算点だと反論しました。
判決では、民法724条前段にいう「損害及び加害者を知った時」とは、被害者が法人である場合には、通常、法人の代表者が「損害及び加害者」を知れば足りるが、法人の代表者が当該法人に対して不法行為を行ったような場合には、同代表者による損害賠償請求権の行使を現実に期待することは困難であり、当該法人は権利の上に眠った者とはいえないから、このような場合にまで時効期間を進行させることは妥当ではないとしました。
このような場合には、単に上記代表者が「損害及び加害者」を知るだけでは足りず、法人の利益を正当に保全する権限のある上記代表者以外の役員または従業員において、損害賠償請求権を行使することが可能な程度にこれを知った時から時効期間が進行するものと解するのが相当であるとしました。
そのうえで、不当な利益を受けていない役員が、この送金システムについて聞いた時点で時効期間の起算点としました。
結局、消滅時効期間は経過しておらず、被告の主張を排斥しています。
不法原因給付ないし信義則違反または権利濫用は?
被告らは、本件システムが不法行為に該当するのであれば、それは、被告らと原告との共同不法行為となるとし、原告の被告らに対する損害賠償請求は、不法原因給付の返還を求めることとなり、認められないと主張。
報酬にあてるべき費用を警備委託料に上乗せしたとすれば、それは、原告が、利益の一部を経費として処理し、法人税等の税金を免れようとする脱税行為だと主張したものです。
さらに、今回の請求は、信義則に反し、または権利濫用であり、許されないとも主張しました。
しかし、判決では、本件システムは、原告の代表者であった被告Y1及び被告Y2が、原告の利益を犠牲にして私益を図るために実行したものであり、かかる行為は、原告と代表者との間の委任契約の趣旨に反するものであるから、代表者による行為であるからといって、被害者である原告自身による不法行為と同視することはできないとし、本件請求を認めることは、民法708条の趣旨に反するものでもないとして、被告の主張を排斥。
信義則、権利の濫用主張についても同様のスタンスで排斥しています。
過失相殺は?
被告らは、仮に、本件訴訟に係る損害賠償請求が認められるとしても、本件システムの構築・実施には原告も関与しているから、極めて大幅な過失相殺がされるべきだと主張しました。
しかし、判決では、本件システムを構築・実施したのは、被告Y1と被告Y2であって、原告であるということはできないとしました。
本件システムは、第三者を巻き込んだ巧妙な利益還元方式であり、簿外の手法であるから、原告内部の者であっても、容易に認識し得るものではなく、過失相殺を認めるに足りる事情は存在しないとして、主張を排斥しました。
以上から、会社の代表取締役であったとしても、会社から報酬以外に個別の利益を得る際には、しっかりと手続きをとるか、全株主から書面での同意を得るくらいのことをしておかないと、退任後に責任追及されるリスクがあるといえます。
企業に関する損害賠償請求の相談も多く取り扱っていますので、ご相談ご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。