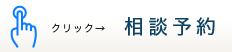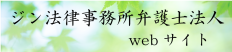FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.裁定和解の手続とは?
民事裁判を進めるなかで、裁定和解という言葉が出てくることがあります。
裁判上の和解手続の一つですので、解説します。
この記事は、
- 民事裁判で、和解の話が出てきた
- 裁定和解という言葉が出てきて混乱している
という人に役立つ内容です。
裁定和解とは?
裁定和解とは、裁判上の和解のなかで、特殊な手続で進める和解です。
あまり利用されていませんでしたが、ウェブ裁判のように、弁護士が裁判所に出頭せずに進める手続の中で、和解が成立するケースで使われています。
実際に使われるのは、和解の合意ができた後の手続のことが多いです。
裁定和解の申立て
裁判所は、当事者共同の申立てにより、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができるとされています(民訴265条2項)。
この手続を使っての和解が裁定和解です。
そこで、まず、当事者双方が裁定和解の申立をします。FAXでも可能です。
この申立書には、原告であれば、被告と共同して、裁判所が定める和解条項に服することによって本件訴訟を解決することとしたので、民事訴訟法265条の規定に基づき、裁判所が事件解決のために適当な和解条項を定めるように申し立てるとの記載をします。
裁判所によっては、書式を送ってくれ、代理人が押印して送るだけで済むこともあります。
この申立は、原告、被告双方がする必要があります。
共同申立であれば別の書面でも良いとされていますので、通常は、別の書面になるかと思います。
裁判所が和解条項を決める
その後に、裁判所が和解条項を定めるとされています。
ただ、実務上は、このような裁定和解の申立がされる前に、和解協議が進められており、和解条項まで詰められていることがほとんどでしょう。
事実上、申立書類の書式などが送られると同時に、和解条項案も来ていることが多いです。
和解条項の告知
裁判所が和解条項を定めたら、これを当事者に告知します。
この告知もFAXで進められ、受領書を送ることで告知の確認がされます。
裁定和解の成立については、和解条項が、口頭弁論等の期日等において当事者双方に告知されたときとされます。
当事者双方への告知日がずれる場合には、遅い方の日に和解成立となります。
ただ、裁判所は、告知を送ったら、すぐに受領書を出すように求めてきます。
裁定和解への不服申立てはできない
裁定和解の場合には、当事者の申立で和解を承諾すると事前に伝えているので、裁判所の和解条項に対する不服申立てはできません。
裁判官が和解条項案を告知する前であれば撤回できるとされていますが、告示後は不服申立てできません。
そのため、通常は、和解条項のすり合わせをして、事実上の合意ができてから、手続き的に使われることの方が多い印象です。
ただ、理論上は、和解交渉が進み、わずかな差で合意ができない、あとは裁判官に任せる、という事案では、活用されることもあります。
和解調書の送付
その後、裁判上の和解と同じように、和解調書が作成され、郵送されてきます。
和解の内容が実現されず、強制執行などをする場合には、この和解調書を使うことになります。
和解調書には、和解成立日に告知日が記載され、FAXで告知した場合には、年月日とファクシミリによる告知である旨が記載されています。
ウェブ裁判と裁定和解
当事者双方の弁護士が裁判所に行くのであれば、裁判所で和解条項を確認すれば、裁判上の和解が成立します。
しかし、新型コロナウイルス蔓延以降、裁判も少しずつウェブが導入されたり、電話会議で進めることが増えてきました。
ウェブ裁判に対応する裁判所も徐々に増えていく見込みです。
そうすると、当事者双方ともが裁判所にいないことが増えます。
そのような場合でも、速やかに和解を成立させる手続として、裁定和解が活用されています。
ウェブとFAXを使うことで、その日に和解を成立させることができるからです。
流れとしては、ウェブの期日で、事実上、合意ができたら、当事者から裁判所へ裁定和解の申立書をFAX(このタイミングで和解条項は事実上できている)、その後、裁判所から和解条項が告知されるFAX、受領書FAXのやりとりで終了となります。
いずれ、FAXも違う手段に置き換わる可能性は高いでしょう。
裁定和解と裁判上の和解案の違い
裁定和解は、裁判所が和解条項を定めるとされていますが、当事者の申立が必要です。
ところが、実際の裁判では、このような裁定和解が突然使われることは少なく、それより前に、裁判官から和解案の提示がされることが多いです。
裁判官からの心証開示、それに基づく和解案が提示されることがあります。裁判官の職権で和解を進めることもあります。
弁論準備期日や和解期日で、そのような和解案がすり合わせられたり、調整されることも多いです。
裁定和解ではない、裁判官からの和解案の場合、当事者はこれを拒絶することもできますが、少なくともその裁判所では、その和解案に近い判決が出されることが見込まれます。
弁護士に依頼しているのであれば、見通しを弁護士からしっかり聞いて、和解に応じるか決めた方が良いでしょう。