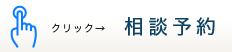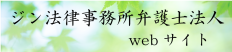FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.生前贈与が無効になる判断ポイントは?
85歳の高齢者の生前贈与を相続人が争った事件があります。医療記録のほか、贈与に至る経緯がポイントになりますので、解説しておきます。
東京高等裁判所令和2年9月29日判決です。
この記事は、
- 生前贈与を無効だと争いたい
- 生前贈与を考えている人
に役立つ内容です。
生前贈与事件の概要
会社関係者に数千万円単位の贈与をし、相続人である子が争ったという事案です。
贈与者は昭和5年生まれ。
株式会社の代表取締役。
被告は贈与者の助手・共同研究者。設立当初から取締役でした。
贈与者は、平成26年1月、転倒負傷して療養生活。
同年2月、心不全により入院。
被告は、同月、代表取締役に就任。
贈与者は、被告に対し、同年3月、法人の全株式を遺贈する旨の遺言公正証書を作成
さらに、贈与者から被告を受贈者とする贈与契約が2件。
平成27年4月付けで3110万円。
同年10月付け2160万円。
これに伴い、贈与者の銀行口座から被告の口座に送金。
贈与は、平成28年7月に交通事故により負傷して入院、平成29年に死亡。
贈与者の相続人は、子2名。長女(控訴人・1審原告)と長男。
長女は医師だったこともあり、贈与者の症状から贈与ができる状態じゃなかったと争いました。
経営していた会社関係の贈与を相続人が争った事件です。
贈与時の意思能力
争われたのは、贈与、資金移動時に、贈与者(85歳)が意思能力を有していたかどうかです。
なければ、贈与は無効。不当利得等として返還義務が出てきます。
一審の判断
一審では、本件各贈与契約は、有効と判断しました。
贈与者の健康不安と長女に対する疑念を背景に、
被告に本件研究所の事業を承継させる目的で、
弁護士や税理士の関与の下にされた一連の株式の処理として行われたもので、
贈与者の意向や関与なくしてできることではないこと、
贈与者が被告に本件研究所の事業を承継させようとした動機は、本件研究所の設立経緯や事業実態に照らして相当なものであること、
贈与者は、元々本研究所の株式全部を被告に遺贈するつもりであったところ、被告から株式の対価が支払われたので、これを被告に戻すために対価に相当する金銭の贈与をしたのであって、そこに不自然なところはないことなどを理由として、これらの送金は贈与者の意思に基づくものであると認定。
当時重度の認知症であったとの主張に対しては、平成21年頃から始まった贈与者の脳萎縮は、進行していたとしても高齢化に伴う緩やかなものと考えられ、平成28年8月に転院し、医師がアルツハイマー型認知症であるとの意見を出す
までは、重度の認知症となっていたと認めることはできないとして、本件各贈与契約とその履行としての送金等の時点では、贈与者が意思能力を欠くということは困難であると判断。
経緯や症状から贈与を有効と判断したものでした。長女が控訴。
高等裁判所の判断
高等裁判所でも、本件各贈与契約の当時、贈与者が意思能力を有していなかったとは認められず、被告への送金等は有効な贈与契約の履行としてされたものとしました。
控訴を棄却するという結論です。
長女が医師だったこともあり、医療記録や医師の意見書等が出されていますが、高裁では詳細にこれらを否定しています。
贈与者の症状
高齢者からの贈与がある場合には、意思能力、判断能力がなかったなどの主張が相続人からされることも多いです。
その際、重視されるのが贈与者の症状。通院している事実があれば、医療記録が重要証拠として検討されます。
本件でも、医療記録から事実認定がされています。
贈与者は、平成21年に実施した頭部CT検査において、軽度の脳萎縮がみられました。
平成28年8月25日に病院で行われた頭部CT検査では、前頭葉、頭頂葉及び側頭葉に有意の脳萎を認め、海馬の萎縮を示唆する両側脳室下角の拡大が顕著であると診断。
平成29年2月13日に行われたMRI検査では、大脳全体が萎縮し、両側海馬で特に顕著であり.アルツハイマー型脳萎
縮のパターンとして矛盾しないと診断され、同日に実施されたSPECT検査では、頭頂葉、模前部、後部帯状回に顕著な血流低下があり、後頭葉でも血流低下が顕著であり、アルツハイマー型認知症に矛盾しない、レビー小体病の合併も疑われると診断。
長谷川式簡易スケール
平成26年2月18日、心不全のため入院していた病院において、実施された改訂版長谷川式簡易知能評価スケール検査(「HDS-R」)を受けた結果、7点。
平成28年8月13日、交通事故による受傷のため入院していた病院においてHDSRを受けた結果、7点。
同月31日、転院した病院においてHDS-Rを受けた結果、6点。
一般に、HDS-Rは、認知症のり患の有無及び程度について補助的な参考資料の位置付けで用いられる簡易検査であり、その結果のみによって認知症の確定診断を下したり、認知症の重症度を判定したりすることは妥当ではないとされており、また、感冒、うつ状態、意識障害などの心身不調や、患者側からの検査に対する協力度などによって結果が左右されることに留意する必要があるとされています。
介護保険の要介護認定
要介護の状態も、意思能力の判断要素として使われることがあります。
今回のケースでは、平成26年4月は要介護4、平成27年2月及び平成28年2月は要支援2にそれぞれ認定されたが、要
介護認定調査における「認知症高齢者の日常生活自立度」の調査結果は、いずれも「I」とされており、要介護認定申請における認知症高齢者の日常生活自立度におけるランク「I」の判定基準は、「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態」とされている(厚生労働省ホームページ)と認定しています。
要介護認定の資料
認定情報に添付された主治医意見書においては、「認知症高齢者の日常生活自立度」はいずれも「自立」とされ、認知症の中核症状である「短期記憶」、「日常の意思決定を行うための認知能力」及び「自分の意思の伝達能力」につい
ては、平成26年4月に「日常の意思決定を行うた
めの認知能力」が「いくらか困難」とされている点を除き、いずれも問題ない旨の記載がされている点を指摘しています。
さらに、 認定資料においては、「意思の伝達は行え、仕事の指示を伝えている」、「日課の理解はできている」、「会社を経営しており、金銭の管理は行っている」、「仕事の指示や判断・取り決めは本人が行っている」等とされ、「短期記憶問題なし」、「自分の意思の伝達能力伝えられる」ともされており、「認知症高齢者の日常生活自立度」の認定調査結果は「I」(何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態)、主治医意見も「認知症高齢者の日常生活自立度」について「自立」とされていることに照らしても、上記の年齢や季節に関する返答状況のみをもって、当時の認知症の程度に関する上記の認定が左右されるものではないとしています。
このような資料では、有利な部分、不利な部分が混在していることも多いですが、偏った主張は採用されにくいでしょう。
医療記録と認知症
本件では、原告である長女は医師でした。
長女は、平成26年2月の時点で贈与者が認知症であることを確信した旨の陳述及び供述をしていました。
しかし、病院からクリニックへの同年4月8日付け診療情報提供書には認知症に関する記載なし。
長女の勤務する病院の診療録には、長女からの伝聞によるものとみられる「平成26年頃から認知症の症状はみられていたようだが」との記戦がある一方で「これまでに専門医の診察は受けていないよう。」との記載がありました。
転院する以前に投薬などの認知症の積極的な治療が行われた形跡はないと指摘しています。
仕事の記録と認知症
贈与者は、平成28年7月21日、救急車・時間外対応で病院を受診。その際の診療録には「2年前に腰椎圧迫骨折の既往ここ数カ月仕事が忙しく、7月18日頃から腰痛再燃した」との記載。
平成28年5月から7月頃にかけて、代表取締役及び信頼性保証業務責任者として、経済産業省による○等に係る試験を実施する試験施設に関する雅準の適合性審査の査察等に対応するなど、精力的に仕事を行っていたことが推認されるとしています。
医療記録から仕事の状況を認定している流れです。
仕事などをしている場合には、そのような活動記録も参考になるでしょう。
贈与契約に至る経緯を認定
贈与の有効性を判断する際には、その経緯から、贈与者の動機を認定することも多いです。そのため、経緯の立証も必要でしょう。
今回、判決でも、次のような経緯を認定しています。
被告は、昭和59年から平成12年まで、○大学において、贈与者の共同研究者・助手として研究の業務に従事してきたが、同人の定年退職を機に、同研究所で行っていた○の安全性能評価試験業務を継続するため、同年4月、贈与者とともに、2500万円ずつ出資して本件研究所を設立。
贈与者が代表取締役に、被告が取締役に就任。
被告は、本件研究所の設立前後において、借入資金の調達、研究所建物の建設、関係行政庁への提出書類の作
成、委託者の承認等に関する実務を担い、本件研究所の設立後は、贈与者の共同経営者として、○の安全性評価等の試験の実施試験委託者への対応、監督官庁である経済産業省による査察等への対応などの本件研究所の事業を同人と共同で執行し、設立時に借り入れた7000万円を15年で返済するなど設立後の経営は順調であったと認定しています。
そして、贈与者は、本件研究所の事業を安定的に継続させるため、被告にこれを承継すべく、平成25年5月、定員を満たす目的で名目的に本件研究所の役員に就任していた長女らを任期満了による退任とし、本件研究所の役員を贈与者と被告のみの取締役2名の体制とした上で、同年11月、本件研究所の株式10株を被告に無償譲渡し、これにより、被告は、本件研究所の過半数の株式を有する株主となっています。
贈与者は、平成26年1月1日、本件研究所のエレベータ内で転倒。
贈与者は、本件転倒事故以来、本件研究所の事業承継を急ぐようになり、病院を退院した翌日である同月21日、同人が所有する本件研究所の株式の全部を被控訴人に遺贈する旨の自筆証書遺言をするとともに、贈与者に加え、被告を本件研究所の代表取締役とする手続を執っています。
そして、贈与者は、同年3月25日、今後の本件研究所の運営を円滑かつ永続的に行うために本件研究所の株式の全部を
被告に遺贈する旨の公正証書遺言をしました。
さらに、被告への株式譲渡を確実に行うべく被控訴人が適正価格での株式買取りを申し出たため、同年2月25日、贈与者と被告との間で、本件研究所の株式157株を代金1774万1000円で譲渡する旨の株式譲渡契約書が作成され、同月26日、同額が送金。
また、同年12月26日、贈与者と被告との間で、本件研究所の株式333株を代金3496万5000円で譲渡する旨の株
式譲渡契約書が作成され、同月29日、同額が送金。
その後、贈与者は、本件研究所の事業への被告の多大な寄与・貢献(本件転倒事故後の付添い介助を含む。)に報い、被控訴人による本件研究所の事業の継続に資するため、被控訴人から支払われた本件研究所の株式譲渡代金を返したいと希望し、話合いの結果、上記譲渡代金相当額の金銭を被告に贈与することとなり、本件各贈与契約が締結されたという経緯を認定しています。
他の相続人との関係を認定
一方、長女は、本件研究所の設立当初は、本件研究所の取締役に就任したものの、取締役の員数を満たすための名目的なものであり、平成25年5月31日に任期満了で退任するまで、本件研究所の業務に関与することはありませんでした。
また、贈与者は、平成25年3月頃から、頻繁に自宅に出入りする長女に対し、財産を危うくするおそれがあると考えて不信感を抱くようになり、長女と贈与者の間の信頼関係は希薄になり、長女が贈与者のことに口を出すことを拒絶するようになっていったと認定しています。
裁判所は、以上の諸事情を総合し、本件各贈与契約は、贈与者が、自らの健康不安と長女に対する不信感を背景に、大学の共同研究者・助手として約16年、本件研究所の共同経営者として約15年にわたり安全性評事業を共に行ってきた被告に対する事業承継の一環として行われたものと認められると認定しています。
被告の功労に報いるとともに、自らの死後も被告によって本件研究所の事業が安定的に継続することを企図したものと認定しています。
贈与契約に至る経緯に不自然な点はなく、各贈与契約を締結したことには合理性が認められるという内容です。
契約内容のシンプルさ
また、本件各贈与契約の内容は、被告から支払を受けた株式談渡代金の返戻として、贈与者が同額の金銭
を贈与するという単純なものであり、当時の心身の状態及び稼働の状況等に照らせば、当該各契約の締結当時、贈与者においてこのような各契約の内容を理解することに特段の支障があったとは認められないとも言及。
贈与などの契約内容のシンプルさも有効性の判断ポイントになります。
認知症でも贈与は有効
贈与者は、平成27年7月及び10月の時点で、初期の認知症を発症していたことはうかがわれるものの、少なくとも単純な内容の意思決定をする能力は十分に有していたものと認められ、このことに、本件各贈与契約に至る経緯、本件各贈与契約の内容等の諸事情を併せ考慮すると、平成27年の本件各贈与契約当時、贈与者が本件各贈与契約の内容について自ら意思決定をするに足りる意思能力を欠いていたと認めることはできないというべきであると結論づけました。
贈与による送金は、贈与者が自らの意思により締結した有効な本件各贈与契約に基づくものであり、法律上の原因なくされたものとはいえないとしています。
医師の意見書等を不採用に
裁判所は長女側が提出した医師の意見書等を否定しています。
k医師は、贈与者が平成27年頃においても当然に高度の認知症であったと考えるのが自然である旨の意見を記載しているが、k医師は、医師である長女と同じ病院に勤務する医師であり、その意見には長女の申述内容や意見が一定の影響を及ぼしていることが想定されることなどから不採用。
教授の意見書も提出されていましたが、贈与者を実際に診察したことはなく、他の医師が診察した際の限られた情報に基づいて意見を述べているにとどまると指摘して、否定しています。
生前贈与の有効性ポイントまとめ
高齢者による生前贈与契約では、死後、相続人から当時の被相続人の意思能力が問題だと主張される事例は多いです。
遺言書があっても、遺言能力がなかったとして、遺言無効確認訴訟が提起されることもあります。
そのような場合に、意思能力があったのか判断されるポイントとしては、本件でも取り上げられたような点が注目されるでしょう。
まずは医療記録、症状の主張。
要介護認定などがあれば、その際の調査結果資料も重要視されます。
それ以外に、贈与などの契約内容の複雑さや、そこに至る経緯、相続人との関係などが主張ポイントになります。
生前贈与、遺言能力等が問題になっている場合には、参考にしてみてください。
生前贈与無効に関する法律相談は以下のボタンよりお申し込みできます。