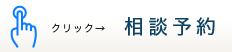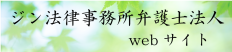FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.親子法改正のポイントは?
民法改正により、嫡出推定、嫡出否認、認知無効の訴えなど、親子関係とくに父子関係の戸籍周りの規定が変更になりました。
今回の親子法改正について整理しておきます。
この記事は、
- 父子関係のルールを確認したい人
- 嫡出否認、認知無効などを検討している人
に役立つ内容です。
親子関係の法改正
民法の親子問題に関する改正がありました。
児童虐待の防止と無戸籍者問題の解消に焦点を当てています。
民法の改正では、
・懲戒権の制限
・嫡出推定、再婚禁止排除、嫡出否認の見直し
・認知無効の見直し
が行われています。
これに関し、国籍法では、認知の効力として、事実に反する認知で日本国籍を取得できないことが明確にされたり、人事訴訟法と家事事件手続法では、嫡出否認通知として、嫡出否認の判決や審判が確定したら、前の夫にもその事実を知らせるなどのルールが整備されるなどしています。
懲戒権の制限に関しては直ちに施行、他の規定については主に令和6年4月1日以降となっていますが、細かいルールは以下の解説を参考にしてください。
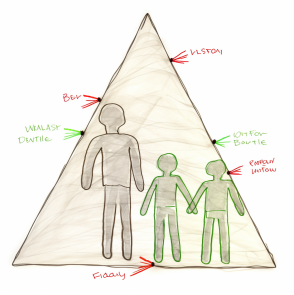
親による懲戒権の見直し
児童虐待の問題が深刻化していることから、懲戒権の見直しがされました。
懲戒権を定める旧法822条の規定は削除され、体罰も明確に許されないものとされています。
居所指定権を定めていた旧民法821条を改正後民法822条とし、新たに改正後民法821条において親権者の監護教育権や、子の人格を尊重する義務を明記しています。
民法820条では、子の利益のために行われる監護及び教育について書かれています。821条は、その範囲を更に具体化・明確化するための規律とされます。
改正後の民法821条は、親が子に対して行う監護と教育に新しいガイドラインを設けます。特に、体罰や精神的な苦痛を与える行為は厳しく禁止されています。これは、以前から児童虐待防止法でも規定されていたものです。
昔から体罰は児童虐待防止法で禁止されていましたが、改正後の民法では精神的苦痛も禁止すると明示しています。
体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁止するとの規律です。
また、この法律では、子供の年齢や発達程度に配慮すること、そして子供の人格を尊重することも求められます。これは、親が子に過度な要求をする、あるいは自分の価値観を押し付けることが問題とされているからです。
懲戒権見直し規定の施行期日
この改正法は、公布された日からすぐに施行されています。つまり、これは「即効性」のある法律です。
令和4年12月16日から、既に施行されています。
嫡出推定規定の見直しの趣旨
旧制度では、戸籍に記載されない「無戸籍者」問題がありました。
改正法は、出生届を提出しやすくし、無戸籍者を減らす狙いがあります。
そもそも、嫡出推定制度の趣旨は、法律上の父子関係を早期に確定することで、子の利益を保護する点にあるとされていました。
無戸籍者問題は、前夫と婚姻中に、夫以外の者との間の子を出産した女性が、出生届を出すと、戸籍上その子は、前夫の子と記載されてしまうことを避けるため、出生届を提出せず、戸籍に記載されない子が出てきてしまうという問題でした。
このような問題が出てしまうのは、嫡出推定制度の趣旨に反するため、改正がされたという経緯です。
出生時の嫡出推定の改定
婚姻前に懐胎し、婚姻後に出生した子については、法改正により子は嫡出と推定されるようになります(改正後民法772条1項後段)。
改正前民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する旨の規定があるだけでした。しかし、でき婚、授かり婚と呼ばれるような、妊娠後に婚姻したケースでも、嫡出子として良いことがほとんどでした。
そこで、婚姻前に懐胎した子でも、婚姻が成立した後に生まれた子には、一律に嫡出推定を及ぼしたほうが合理性が
あるとされました。
2回以上の結婚と嫡出推定
二つ目の改正は、特に複雑な家庭環境に対応するためのものです。もし女性が妊娠中に2回以上結婚していた場合、どの夫が子の父親かを明確にする新たな規則が設けられました。具体的には、最後の婚姻の夫が父親とされます。
2回以上の婚姻とは、前婚で妊娠、離婚、再婚して出産というような場合です。
今般の改正においても、婚姻解消日から300日以内に生まれた子は婚姻における夫の子と推定するとの規定はのこされています。
一般的な妊娠期間からして、婚姻解消から300日以内に生まれた子については、その懐胎時期が婚姻中である蓋然性が高いからです。
しかし、女性が子を懐胎した時から子の出生の時までに2回以上の婚姻をしていた場合は別問題です。
この場合、2つの推定がぶつかります。
婚姻解消から300日以内なので、前婚の夫の子との推定。
これに対し、婚姻前に懐胎、婚姻成立後に出生した子の推定という新しい規定。
この2つの推定がぶつかったとしても、改正法では、重複する推定のうち、子の出生の直近婚姻の夫の子との推定を優先させました。
再婚している以上、再婚後の夫の子である蓋然性が高いと思われます。
そもそも、無戸籍者問題は、生物学上の父子関係がないのに、前夫の子と推定されることにあった点からしても、再婚後の夫の子との推定を優先させたほうが、無戸籍者問題にはつながりにくくなります。
嫡出否認がされた場合における子の父を推定
改正後の民法772条3項では、女性が妊娠から出産までに2回以上の結婚がある場合、最後に結婚した夫を子の父と推定するようになっています。
しかし、もし最終婚の夫が子の父でないと否認された場合、その推定は無かったことにされます。この場合、重複していたものの推定が劣後していた前の夫の推定が活きてきます。
改正後民法772条4項では、改正後民法772条3項の規定の適用については、嫡出否認の手続によって子がその嫡出であることが「否認された夫との婚姻を除き」、子の出生の直近の婚姻における夫の子と推定するとの規定になっています。
嫡出否認がされると、優先推定がなくなるので、前の夫の推定が昇格するイメージです。
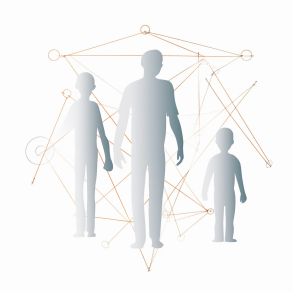
女性の再婚禁止期間の廃止
改正前、女性は前の結婚が解消されてから100日は再婚できませんでした。
再婚禁止期間と呼ばれていました。
これは、改正前民法733条1項が、婚姻成立から200日を経過した後又は婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は婚姻における夫の子と推定するとしており、推定が重複する問題があったために設けられていた制度でした。
しかし、新しい規則では最終婚の夫を子の父と推定することになったため、この100日の規定が必要なくなりました。これは女性の再婚の自由を高め、平等性も向上させます。
嫡出改定の施行期日及び経過措置
改正法は基本的に公布日から1年6ヶ月以内に施行されます。施行期日は、令和6年4月1日と決められました。
新しい推定の規則は、施行日以後に生まれた子にしか適用されません。それ以前に生まれた子には、以前の規定が適用されます。
嫡出否認制度の見直し
嫡出推定関係以外に、嫡出否認も改正がありました。
旧民法では、結婚している男性が法的に子供の父とされました。
この父子関係を変更するには、夫だけが「嫡出否認の訴え」を起こせました。さらに、この訴えは子の出生から1年以内にしなければなりませんでした。
この制度は、子供の地位を早く安定させる趣旨のものでした。
しかし、この方法が全ての家庭に合うわけではないとの指摘がありました。それは、状況によっては母親や子供自身が父子関係を変更する必要がある場合もあるからです。
新法では、この問題を解決するために、嫡出否認の訴えを母親や子供も起こせるようにしました。さらに、訴える期限も1年から3年に延長されました。
子も嫡出否認の訴えが可能に
子供自身にも、自分の「法律上の父親」が本当に自分の父親か否かを訴える権利が新しく付与されました。
子供がまだ小さい場合、母親や法定代理人が子供の代わりに訴えを起こすことになります。実際には、期間が出生から3年のため、法定代理人が提訴することになるでしょう。
母の否認権については、権利の行使が子供の利益を害する場合は制限されます。
さらに、再婚後の夫の子と推定される子の場合には、前夫にも否認権が認められています。
法改正により、母の再婚により父性推定が重複すると、再婚後の夫の子との推定が優先されることになっています。これに対し、前夫が自分が生物学上の父であると主張する手続きとして、否認権が認められたものです。
前夫の行使も、子供の利益を害する可能性がある場合は制限されます。
また、子が成年に達した後はこれを行使することができないという制限があります。
嫡出否認の出訴期間の伸長
改正前の民法では、夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさなければなりませんでした(改正前民法777条)。
改正後の民法では、この期間を1年から3年に延長しています。
起算点は、人によって異なります(改正後民法777条)。
母や子→出生時から。
夫や前夫は、認識時から。
子による嫡出否認の期限の特例
子が21歳に達するまでの間は、子が自らの判断によって嫡出否認の訴えを提起することができることとされています。この例外規定が使えるのは、子と父との間に社会的な実態としての親子関係が存在しない場合に限るのが相当とされています。
父子の同居期間が、3年を下回るときに限ります。
同居期間が2つ以上あるときは、そのうち最も長い期間で判断されます。
もっとも、同居期間が3年を下回っても、養育状況から、社会的な実態としての親子関係が存在するといえる場合には、子による否認権の行使が父の利益を著しく害するとして、否定されます。
繰り上がり前夫の否認期限
再婚後の夫が父ではないと確定した場合、前夫が父と見なされます(改正後民法772条4項)。
この状況でも、前夫や子、母は新たな否認権を行使できます。前夫の嫡出推定も否認するという場合です。しかし、この権利を行使する期限は、再婚後の夫が父でないと確定した裁判を権利者が知った時から1年と定められています(改正後民法778条)。こちらは、3年ではなく1年ですので注意が必要です。
重複する2つの推定とも否認する場合ですね。
嫡出の承認の見直し
改正前の民法776条では、子が生まれた後、夫がその子を嫡出子として認めると、夫が後から否認する権利は失われました。
改正後の法律では、母にも同様の規定ができました。改正により、母にも嫡出否認の権利が認められたことから、夫と同じように承認後に否認する権利が否定されています。
子の監護費用の償還制限
改正後の民法では、たとえ父子関係が否認されたとしても、父が負担した子の監護費用を子が返さなくてもよいと規定されています。
これは、子が「否認をためらう」といった不安を抱えないように、そして子の最良の利益を守るための規定です。
父は、子に対して扶養義務を負っています。
嫡出推定が否認されれば、本来は、扶養義務を負っていなかったことになります。
理論的には、子の監護費用は、不当利得の返還請求の対象となりえます。
しかし、このような請求を認めると、子による否認権が使いにくくなるため、制限されたという経緯です。
嫡出否認と相続
改正後の民法778条の4では、もし前の夫が亡くなり、その後に新しい夫との子の父子関係が嫡出否認され、前の夫が実父であったとされた場合、既に分割された遺産については、「金額のみでの補償」が認められることになりました。
これは、遺産の状況を不安定にしないため、そしてすでに分割が行われている場合の混乱を避けるための規定です。
嫡出否認と当事者の死亡
嫡出否認と当事者の死亡も整理しておきます。
まず、嫡出否認を請求する権利者である夫が死亡した場合ですが、夫が死亡した後でも、一定期間内に子や相続人は嫡出を否認する訴えができます。嫡出子がいることで相続権を害される者などの利害関係者による訴えや引き継ぎができます。このルールは改正前後で変わりません。
次に、法改正で、嫡出否認請求ができることになった子や母、前夫が死亡した場合ですが、この場合には、同様の規定が作られませんでした。
嫡出否認訴訟中、被告(子)が死亡した場合、訴訟は自動的に終了します。このルールも変わりません。
嫡出否認訴訟中、被告(父)が死亡した場合、訴訟は自動的には終了しないようになっています。この場合、検察官が被告になります。
子の法律上の父が誰であるかは、父の死亡後でも、子の氏や戸籍、相続等に関係するため、訴訟は当然には終了しないとされました。
複数回の離婚と再婚
女性が懐胎から出生までに3回以上の複数回婚姻した場合、嫡出を否認できる前夫が褐数存在するようになります。
一つの嫡出否認の訴えが認められると、他の前夫が法的な父になる可能性が出てきます。
そこで、嫡出否認の訴えを起こそうとする前夫は、他の前夫も含めた複数の被告に対して嫡出否認の訴えを一緒に提起しなければならなくなっています。
この訴訟については、弁論も分離できないものとされています。
嫡出の否認通知
新しいルールでは、前夫にも子の嫡出否認の判決内容が通知されることになりました。
再婚後の夫の子との嫡出推定が否認された場合、前夫の子と推定されます。しかし、前夫は、自らが原告となっていなければ、通常は、嫡出否認の結果を知りません。
これは、新たな父親が子を適切に養育する前提として、責任を認識させるためにも、情報を伝える必要があることから通知がされることとなりました。
これにより、前夫は、自身の嫡出否認権利を使うことができる立場になったと知ることができます。
通知は、嫡出否認の判決が確定したときに、裁判所からされることになっています。
嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときも同じです。
生殖補助医療法の変更
改正前生殖補助医療法という法律の10条では、嫡出否認が制限されています。
具体的には、妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子で生殖補助医療により懐胎というケースです。
このような場合、夫は、嫡出否認をできないとされていました。
もともと生殖補助医療を使っている以上、生物学的に父子関係にないことは明らかなため、夫の否認権を制限したものです。
今回の法改正で、新たに子や母にも否認権が認められましたが、同様の生殖補助医療の場合には、子及び母も否認権が
制限されることとなっています。
嫡出否認改正の施行日
施行日は、令和6年4月1日とされています。
基本的には、改正後の法律は新しく生まれる子に適用されますが、一部の制度は、施行前に生まれた子に対しても適用される扱いになっています。
父による嫡出の否認の訴え、前夫による嫡出の否認の訴え等については、施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子について適用されます。
これに対し、子又は母による嫡出の否認の訴え等については、施行日前に生まれた子についても適用されることになっています。この場合の嫡出否認の訴えの出訴期間は、改正法の施行時から1年とされています。

認知無効の訴え
認知無効の訴えについても改正がありました。
認知は、婚外子でも、父子関係を発生させるものです。認知がされ、父子関係があっても、これを無効だと争う場合の話です。
改正前の法律では、子や利害関係人が認知無効の訴えを起こせるとされていました。しかし、これには、範囲が曖昧で広すぎるとの批判もあり、認知関係の安定性が乏しかったと指摘されています。
嫡出否認の訴えでは、提訴権者も出訴期間も厳しく制限されているとの均衡も問題になりました。
新しい法律では、認知無効の訴えに厳格な規則を設けることで、子供の安定した身分を保証しようとしています。
具体的には、認知の無効の訴えを提訴できるのは、子、その法定代理人、認知をした者及び子の母に限定されました。利害関係人というような曖昧な規定を明確にしたものです。
また、認知の無効の訴えを起こせる期間としては、認知をした者については認知の時から、子又はその法定代理人及び母については認知を知った時から、それぞれ7年とされました。
ただし、母による認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、母による主張は認められないとされています。
認知無効訴えの提訴期限
以前は期限がありませんでした。
これに対し、改正法では、一定の事情から7年以内に訴えなければならないという制限があります。
7年がいつからスタートするかについては、人によって違います。
子又はその法定代理人、母については認知を知った時からスタートします。
認知をした本人については認知の時からとされています。
特例として、子が21歳になるまでは一定の条件下で訴えが可能とされます。
子は、認知を知ったとしても十分な判断能力がないために認知無効の訴えを起こせないことがあります。
子が21歳に達するまでの間は、子が自らの判断によって認知無効の訴えを提起することができることとされています。
ただし、嫡出否認の訴えと同じく、この特例は、子がその父と継続して同居した期間が3年を下回るときに限り適用されることとされています。また、子による認知の無効の主張が、認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、提訴は認められないとされています。
認知無効でも監護費用の請求制限
認知が無効だとされたとしても、父親が出した子の監護費用を子は返さなくてもいいものとされました。
これは子の利益を保護するためです。
認知が無効とされた場合には、父子関係は子の出生時に遡ってなかったものとされます。
そのため、本来は、父が負担した監護費用は、不当利得として返還請求しうるものです。
しかし、嫡出否認でも、このような費用請求を制限しています。
同様に、このような請求を認めると、認知無効の訴えも起こしにくくなるため、子は、償還する義務を負わないものとされました。
胎児認知の見直し
女性が婚姻前に妊娠し、婚姻後に出産した場合、改正後の民法772条1項後段により、その子は夫の子と推定されます。この推定が胎児認知(民法783条1項)よりも優先される形になりました。認知は、出生前、胎児の状態でも母の同意があればできます。
出産前に胎児認知される、母が別の男性と婚姻、出産したというパターンです。
そのような子について胎児認知がされていたとしても、効力は生じないことになります。
胎児認知には母の承諾があります。
しかし、母が、その後、別の男性と婚姻したということは、そちらの子とした方が良いようにも感じます。
実際には、どちらのパターンもありうるものであるところ、子の立場からすれば、母の婚姻を基礎とした嫡出子の方が身分関係が安定するという考えから、婚姻した夫の子との推定が優先してされることになりました。
つまり、胎児認知をされても、嫡出推定によって子の父が定められるとき(婚姻後に出産等)は、胎児認知は効力を生じないものとされました。
当事者の死亡と認知無効の訴え
認知の無効の訴えの原告や、原告となり得る者としての認知をした者が死亡した場合、嫡出否認の訴えの場合の規定が準用されています。
同じように、子のために相続権を害される者等も、一定の期間内に限り、認知無効の訴えを提起したり、訴訟手続を受け継ぐことができます。
認知無効の訴えの経過措置
胎児認知と嫡出推定との調整規定(改正後民法783条2項)は、施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子について適
用されます。
認知の無効に関する規定は、施行日(令和6年4月1日)以後の認知について適用されます。
施行日前の認知に対する主張は、 改正前民法の適用となります。
親子問題に関する法律相談は以下のボタンよりお申し込みできます。