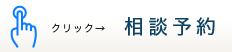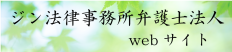FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.訴えの取下げの手続きは?
民事裁判を起こしたり、起こされた後、訴えを取り下げるという場合があります。
その際の手続きや要件について解説します。
この記事は、
- 民事訴訟の訴えを取下げたい
- 訴えを取り下げてほしい
という人に役立つ内容です。
訴えの取下げとは
訴えの取下げは、民事訴訟・民事裁判で原告が起こした訴えを自らやめるように申し出ることです。
訴えの取り下げがあると、民事裁判は初めからなかったものとされます。
民事裁判は終了となります。
最初からなかったことになるので、裁判となった紛争は裁判では何も解決されません。何も判断がされないことになります。
訴えの取下げの条文は、民事訴訟法261条以下に書かれています。
民事裁判の終わり方
訴えの取下げは、このように、民事訴訟の終わり方の一つです。
民事訴訟・民事裁判の終わり方にはいくつかあります。
民事訴訟法では、判決、訴えの取下げ、請求の放棄、請求の認諾、訴訟上の和解の5つが終了事由として予定されています。
判決は、裁判所が判断を下すもの、請求の放棄は原告が請求を断念するもの、請求の認諾は被告が請求を認めるもの、訴訟上の和解は、裁判手続の中で原告と被告が和解する手続きです。
訴えの取下げは、民事裁判の終わらせ方の一つで、請求の放棄に似ていますが、請求を断念してあきらめて確定させるというものではなく、一度、手続きをやめるというものです。
訴えの取下げの効果
訴えの取下げの効果としては、訴えが取下げられた部分の裁判が、初めから係属していなかったものとみなされます。
訴えの全部が取り下げられると民事訴訟は終了となります。
初めから訴えられなかったものと扱われるものです。
最初から訴えられなかったということは、訴え取下げ後に、再び同じ訴えを提起することもできるのが原則です。
そのため、理論的には、訴え取下げ後、再度訴え提起、訴え取下げ、再度訴え提起とループする危険性もあります。
訴え取下げの濫用を防止する趣旨から、本案の終局判決後に訴えを取下げた者は、同一の訴えを提起することは禁止されています。これを再訴禁止効と呼びます。
以前は、消滅時効の中断について、訴え提起があると時効中断、その後に訴えを取下げると初めから訴えなかったものとされ、時効中断の効果は消滅するとされていました(旧民法149条)。法改正により、裁判上の請求は時効完成猶予とされたので、この条文は削除されています。
訴えが取り下げられる場合とは
このような訴え取下げは、どのような場合に使われるのでしょうか。
訴えを提起したものの、訴えを続ける必要性、理由がなくなった場合に使われることが多いです。
訴え提起後に、裁判外で和解ができたり、支払いがされるなど目的を達成できたので、訴えの取下げるという使われ方です。
または、被告の反論を受け、請求断念により、訴えを取り下げるというケースもあります。
そのため、被告の立場から訴訟を取り下げてほしい場合には、
・しっかり反論して請求を断念させる
・裁判外で交渉、和解する
という対応となります。

訴え取下げと裁判費用
訴えを取り下げること自体に費用はかかりません。
裁判を早期に取下げた場合、訴え提起手数料(訴状に貼った印紙)が一部還付される場合があります。
最初の口頭弁論期日の前に訴えを取り下げた場合、印紙還付の申立てをすることで、貼った印紙の2分の1の額が還付されます(最低額の基準はあり)。
訴え取下げの方法
実務上、訴えの取下げは書面でされることがほとんどです。
法的には、原則として書面、例外的に裁判期日では口頭で取り下げることもできます。
裁判期日とは、口頭弁論期日、弁論準備手続期日のほか、和解期日、進行協議期日などのことです。
書面での訴え取下げでは、原告から訴えの取下げ書が裁判所に提出されます。この訴えの取下げ書の副本が被告に送達されます。訴えの取下げ書はFAX送信では認められておらず、郵送や裁判所に持って行って直接提出します。
口頭での訴え取下げでは、被告がその裁判期日に出席していない場合、期日調書の謄本が相手方に送達されます。
訴えの取下げリスクと被告の同意
訴えの取下げは原告がおこなうものですが、取り下げ後、再び提訴することもできてしまいます。
理論的には、何度も提訴されるリスクがあり、この場合、被告は不利益を受けます。
被告としては、裁判にまでなったのだから、しっかりと裁判所の判断をもらいたい、判決にして解決したいと考えることがあります。
このような被告の立場も考慮し、民事訴訟の提起後、被告が裁判内容を争った後には、被告の同意がなければ訴えを取り下げることはできないとされています。
裁判内容を争うとは、被告から答弁書や準備書面を提出し、期日等で申述をしたり、口頭弁論をした後のことです。
「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」(民事訴訟法261条2項)
内容を争った書面等を提出している以上、被告も裁判の準備をしていることになります。そこで同意もしていないのに、途中で打ち切られ、再度、訴えられるリスクがあるのでは、被告の負担が大きすぎます。
訴えの取下げと同意擬制
このように、被告が動いた後は、被告の同意が訴え取下げの要件になります。
ただ、明確な被告の同意がなくても、同意が擬制されることがあります。
擬制とは、みなすという制度です。法律ではよく出てきます。
同意をはっきりしていないけど、同意したものとみなす制度です。
具体的には、被告が、訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなされます(民事訴訟法261条5項)。
被告がすでに争っており、訴えの取下げには同意しない、裁判所で判断してほしいと望む場合には、2週間以内に異議を出す必要があるのです。
なお、訴えの取下げ書ではなく、口頭での取り下げの場合、2週間の期限については、被告が出席していれば、その期日から、欠席していた場合には期日調書の送達からスタートします。
訴えの取下げの擬制
原告が訴えの取下げをしていないのに、取り下げたものとみなされる制度があります。
訴えの取下げ擬制です。
訴訟追行に不熱心だと、訴訟をする気がないものとして、取下げたものとみなされてしまいます。
具体的には、原告及び被告が、口頭弁論・弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合で、1か月以内に期日指定の申立てをしないと、訴えの取下げがあったものとみなされます。なお、出頭しても何も申述しないで退廷、退席した場合も同様です。この場合、裁判は休止、休止満了で取下げ擬制と呼ばれます。
また、当事者双方が、2回連続して、裁判期日に出頭しなかった場合訴えの取下げがあったものとみなされます。
この場合、取下げたものとみなされるため、原告が、訴えの取下げ書を別に準備する必要はありません
1か月経過又は2連続欠席で取下げ擬制とおぼえておきましょう。
訴えの取下げの期限
ところで、原告はいつまでなら訴えを取り下げることが可能なのかは気になるところです。
まず、被告が争った後は、同意が必要になります。同意があれば、その後も取下げができます。
訴えの取下げは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができるとされています。
つまり、判決が確定するまでなら、被告の同意があることが前提ですが、期限の制限はないことになります。
判決の確定なので、一審の判決が出ても、確定していなければ取り下げができます。
自分に不利な判決が出たので、原告が訴えを取り下げようとすることもできます。ただ、この時点では、通常は、被告の同意が必要です。被告は同意しないでしょうから、訴え取下げの要件を満たさないことになるでしょう。
判決後に、裁判外で和解ができて取り下げるような場合には、この話が関係してきます。
また、判決が出た後の訴え取下げでは、同じ請求について再度、訴えを起こせなくなるという効果が出てきます。
和解と訴えの取下げ
裁判を起こした後、原告と被告との間で和解が成立することもあります。この場合、裁判手続を続ける意味はなくなります。そこで、和解と訴えの取下げの関係も問題になります。
和解方法もいくつかありますが、多くは、裁判上の和解か、裁判外の和解(訴外和解とも呼ぶ)で解決します。
裁判上で和解をすれば、裁判の取り下げを考える必要はありません。裁判上での和解自体が、裁判の終了事由です。
これに対し、裁判外で和解書の取り交わしをした場合は、裁判自体を取り下げる必要があります。裁判外の和解では、裁判手続は止まらないので、取下げをして終了させる必要があるのです。
その場合、通常は原告側から裁判所に訴えの取下げ書を提出し、被告がそれに同意します。
実務では、裁判をした後に裁判外の和解になることも多く、その場合は、和解書や合意書に訴えの取下げ条項や同意条項も盛り込みます。
訴えの取下げでも反訴は残る
裁判では、被告から訴え返す反訴という手続きもあります。
このような反訴がされた場合、もとの原告が本訴を取り下げても、反訴は残ります。
原告としては、訴えを取下げて裁判手続きから解放されたいと考えたとしても、反訴の対応が引き続き必要になります。
和解などで訴えを取り下げる場合には、反訴も取り下げてもらうのが良いでしょう。
訴えの取下げの効力を争う方法
訴えの取下げがされたのに、後からそれを争うということも想定されます。
「訴えの取下げは無効です」という争い方です。
形式的には訴えの取下げがあると裁判は終了になります。
訴えの取下げを無効だと主張のであれば、裁判を復活させなければなりません。
手続き的には、その事件の口頭弁論期日指定の申立てをすることで、訴訟の続行を求めることになるでしょう。
その後、裁判所は、訴えの取下げが有効か無効かを判断することになります。
有効だとすれば、訴訟は終了した旨を宣言する判決をします。
無効だとすれば、訴訟は係属していることになるので、審理を続行することになるでしょう。
中間判決で訴えの取下げが無効だと判断することもあります。
訴えの取下げが無効になる場合
では、どういう場合に、訴えの取下げが無効とされるのでしょうか。
訴えの取下げ書が原告によるものではなく、偽造されたような場合が無効例としては想定されます。
ただ、実務上は、裁判期日間に訴えの取下げ書が届いても、裁判所から代理人弁護士に確認が入ったりすることが多いでしょう。
他に、訴えの取下げが無効になる例として想定されるのが、詐欺・脅迫等による場合です。
取下げ書を提出したものの、被告や関係者からの詐欺や脅迫により、本来の自分の意思ではなかったと主張するものです。
明確に、犯罪行為となるような他人の行為が原因で訴えが取り下げられた場合には、訴えの取下げは無効とされています。
当事者複数の訴え取下げ
原告や被告が複数の裁判もあります。
その中でも、特に、全員の裁判参加が義務になる裁判があります。
固有必要的共同訴訟と呼ばれるものです。
代表的なのが、共有物分割訴訟です。共有している不動産の分割を決める際に、一部の共有者だけが裁判をしても解決につながりません。この場合、全員が原告か被告の当事者になっている必要があります。
このような訴訟で、共同原告の一部だけが訴えを取り下げたり、共同被告の一部だけに対する訴えを取り下げることは許されないとされます。
全体解決ができないからです。
訴えを取り下げる場合には、全員が取り下げる必要があります。
民事裁判に関する法律相談は以下のボタンよりお申し込みできます。